昨年、気仙沼漁師カレンダーの10年の歩みが本になりました。
漁師カレンダーの企画・制作は、このnoteを書いている私たち「気仙沼つばき会」なのですが、つばき会には震災後に移住してきたメンバーも多く、初期の経緯を知るのはひと握り。カレンダーがどのように始まり、続いてきたのか、本を通じて初めて知ることも多く、カレンダーの10年を終えた節目にこのような書籍が刊行されたこと、とてもうれしく感じています。
この機会にぜひ、書籍化の背景を聞かせてもらいたいと、著者の唐澤和也さんと編集者の宮崎幸二さんにお話をうかがいました!前後編に分けてお伝えします。

気仙沼つばき会と気仙沼漁師カレンダーの10年
唐澤和也・著 集英社

著者・唐澤和也さん(左)
編集者・宮崎幸二さん(右)
最初は「気仙沼の女たち」を描きたいと思っていた
ー 今日はお忙しいところありがとうございます!どうやって書籍化が実現したのか知りたいと思っていたので、お話が聞けることうれしいです。よろしくお願いします。
唐澤
こちらこそ、ありがとうございます。
― 先日、気仙沼つばき会のメンバーから、実はカレンダー撮影の頃から唐澤さんが「気仙沼つばき会の話を本にしたい」と言ってくださっていたとうかがいました。構想はいつ頃からあったのでしょう?
唐澤
竹沢うるまさんの撮影のタイミングぐらいだと思うので、2017年頃だと思います。その頃はまだこんなにちゃんとした企画ではなくて、仮タイトルが「気仙沼の女たち」っていう、演歌のタイトルみたいな(笑)
とにかく、気仙沼で出会う人出会う人が面白くてパワフルだったから。僕自身長年インタビューをして書く仕事をしてきたので、人物ごとに区切って紹介するイメージで。でも、当時は本当に漠然とした夢だったんです。具体的なものじゃなくて
― 「気仙沼の女たち」ですか!いいですね。出会った女性たちのどんなところが印象深かったですか?
唐澤
「海と生きる」でも触れたエピソードですが、つばき会の小野寺紀子さんが震災直後にデスクトップパソコンを担いで東京に行った話がありますよね。取引先への支払いを滞らせないように外国送金するために。紀子さんはあの話を、全然お涙頂戴ではなく、何だったらちょっと笑いにしながら喋ってくださったんですね。話を聞きながら、その場ではすごく我慢したんですけど、もう泣きそうになって。
― 遠洋漁業で操業する船に餌や資材がちゃんと届くように、震災からわずか10日後に、デスクトップパソコンを担いで被災した気仙沼から東京に向かったお話ですよね。私たちも度々聞いていますが、本を読んで改めて笑って、泣きました。当時の紀子さんの気持ちが伝わってきて。
書籍全体の構想は変わっても、「海と生きる」でも気仙沼の女性たちの魅力はしっかり描かれていますね。

「気仙沼漁師カレンダー」のライターとして
2作目から10作目まで9年間気仙沼に通い続けてくださった
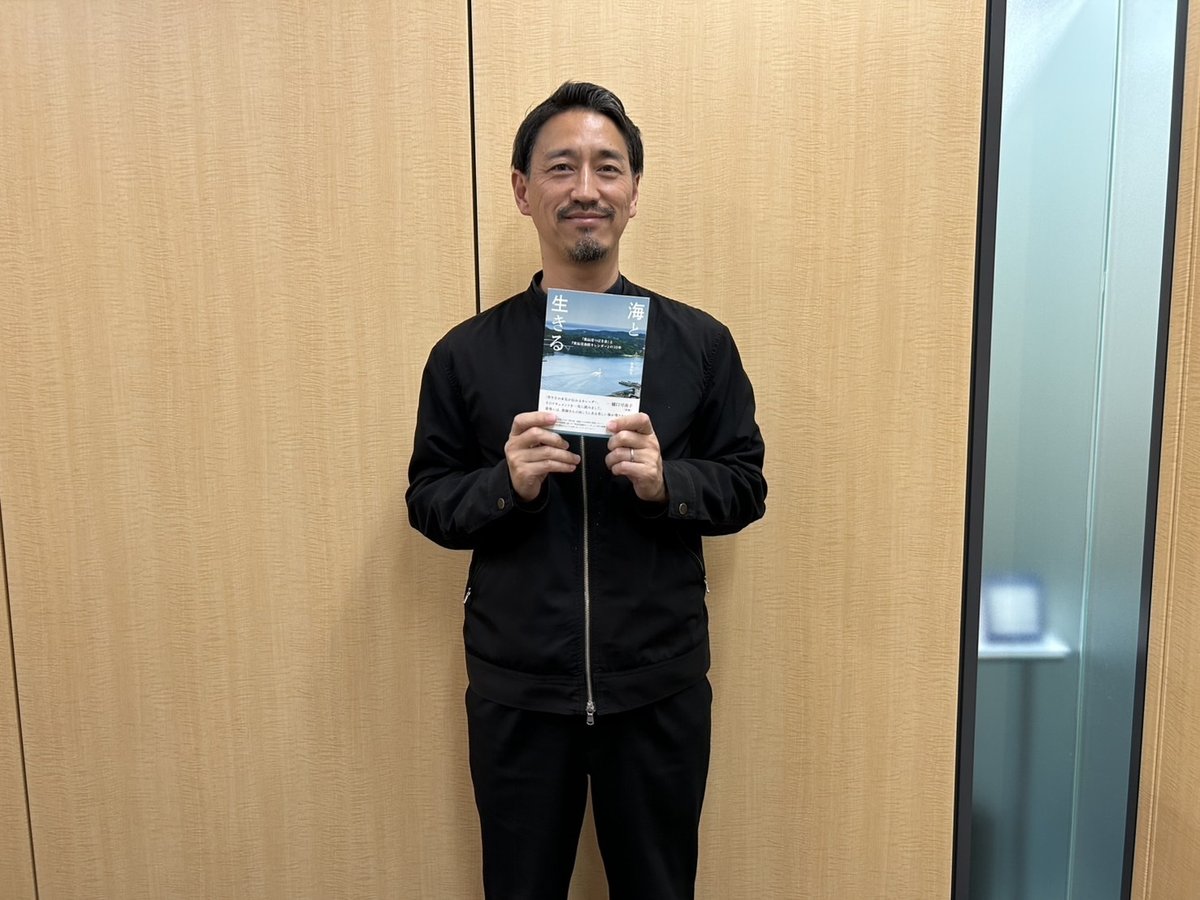
書籍の企画は宮崎さんからだった
ー 書籍化に向けて実際に企画をされたのは編集の宮崎さんだとうかがいましたが、どういった経緯で書籍化につながったのでしょう?
宮崎
僕と唐澤さんとはもう25年ぐらい一緒に仕事をしている仲なんです。新人の時から一緒に「週刊プレイボーイ」で仕事をして。
その後、漫画家の森田まさのり先生の本を唐澤さんに構成していただいて、僕が編集を担当したことがあって、その打ち上げの時に唐澤さんから、さっき話題にあがった「気仙沼の女たち」という本はどうかという話があったんです。すごく面白い人たちがいるんだって。それが2019年9月ですね。
― 「本にしたい」と唐澤さんが、つばき会のメンバーに話された翌々年ですね。
宮崎
ただ、その時はさすがにそれだけでは本にはできないと感じて、「それでは無理だ」と話していたんです。
でもその後も、唐澤さんが漁師カレンダーの話を毎年、機会あるごとにしてくれて、僕自身、写真を扱う仕事もしてきたので、すごいプロジェクトだなというのは感じていたんですね。で、ちょうど10年で瀧本幹也さん撮影のカレンダーで終わるということを知っていたので、これを何かまとめられないかな、と、企画書にしたのが、2023年の10月ですね。
― その時点で、「気仙沼の女たち」の企画は、どのような企画になっていたんですか?
宮崎
もう完全に今の本と同じような企画です。
漁師カレンダーの撮影に携わった10名の写真家さんたちは、普通に考えてなかなかない座組みなので、この方たちを取材したいと。このプロジェクトの成り立ちから、その現場の大変さ、震災後の町の変化をドキュメントで追いたいと思ったので、軸は漁師カレンダーにしました。
漁師カレンダーに関わるつばき会さんと、それを受けて撮影をする写真家さん、その被写体である漁師さん、という3方が絡んでのプロジェクトだったので、そこを描く本として企画しました。
― 漁師カレンダーについて「すごいプロジェクトだ」と感じてくださったというのは、どういう点についてそう思われたのでしょう?
宮崎
シンプルに、この歴代の写真家さんたちをなぜ抜擢できたのか、とか。
僕らも写真集を作ったりしてきたので、漁師カレンダーは、錚々たる写真家さん達が携わっているけれど、実はそんなにバジェットもないんじゃないか?とか、制作の裏側も分かるので、どうやったらこの多忙な写真家さんたちをアサインできたんだろうとか、カレンダーを作る側の視点で見ていた気がしますね。
藤井保さんから始まって、浅田政志さんや川島小鳥さんたちがつなぎ、瀧本幹也さんで締めるという、もうこの並びがめちゃくちゃ魅力的だなっていうのはそもそも思ってたので。だから本当は最初、写真集にしようという話もしていたかもしれません。正式ではありませんが、この企画の前段階で。

藤井保さん、浅田政志さん、川島小鳥さん、竹沢うるまさん、奥山由之さん
前康輔さん、幡野広志さん、市橋織江さん、公文健太郎さん、瀧本幹也さん
錚々たる写真家の方々に手掛けていただいた
― 10人の著名な写真家が、「気仙沼の漁師」をそれぞれどのように撮影したのか、写真集という形で見たい人も多そうですね。
宮崎
でも最終的に作り手の側から考えて、この10人を写真集にまとめるのはちょっと無理だなと思ったんです。写真集ってやっぱり一人の作家さんのものなので、写真の色味や、デザイン、選ぶ紙など、絶対に皆さんこだわりがあるはずだから。ただ写真をオムニバスで収めるものはできるかもしれないけど、それは写真集じゃなくて、展覧会の図版資料みたいなものになると思ったんです。それじゃないなと思った時に、じゃあこのカレンダーに関わった人たちの話をまとめようと考えて。
「震災のことを自分が書いていいのか」からの変化
― 唐澤さんは漁師カレンダーの制作時、気仙沼に9年間通われていますが、その中で描こうとしてきたことと、書籍を通じて表現したいことに変化はあったのでしょうか?
唐澤
ありました。9年間カレンダーの取材で通っていた時に、僕が描くのは漁師なんですよ。つまり写真家さんとは一緒に仕事をするけど、彼らを描こうとは思っていないので、僕にとっての主人公は漁師さんであり、漁業関係者だったんです。
僕、人生初漁師だったんですね。
― あ、初漁師ですか!
唐澤
かつ、人生初気仙沼弁なので
― ははは、初気仙沼弁で初漁師。言葉も濃そう。
唐澤
そうなんです。最初、とにかく何をおっしゃっているのかが全然分からなくて。
それこそ小野寺紀子さんが通訳してくださったりしたけど、もうとにかく必死だったんですよ。
僕が参加し始めた2016年版の浅田政志さんの撮影時は、魚市場の周辺に止まってる船に声をかけて、オッケーをもらったらそのまま船に乗り込んで撮影するスタイルだったんです。船の入る時間にあわせ、2時間仮眠して起きて交渉に行く、みたいな感じで、それを数日間トライし続ける。
どの写真が掲載されるかが分からない中、撮影した漁師さん全員に話を聞いたんです。当然話が面白い方も、あまりしゃべらない方もいる中、10分とか15分の時間でインタビューをしなければいけなくて。
― 気仙沼弁も漁師さん達の語る内容も慣れなくて分かりづらい上に、どの人が掲載されるかも分からないまま次々話を聞いたんですね…それは、本当に大変な取材ですね。
唐澤
もう本当に必死でした。最初はとにかく僕がびっくりしたようなことを伝えようと思いましたね。例えば漁師ってこんなに専門職があるんだということも全然知らなかったので、そうしたこととか。気仙沼以外の人や、気仙沼に暮らしながらも「漁師」を知らない人たちに、彼らの魅力を伝えられたらと考えていました。
その後、2018年版の竹沢うるまさんの頃から、撮影と文章の取材が同時進行ではなくなって、写真を決めてレイアウトを決めてから文章の取材をするスタイルになったので、そこからは感動や物語も描いていけたらという感じになっていったと思います。
でもトータルで思っていたのは、カレンダーなので写真が主人公であるということです。僕は豪華な「おまけ」になりたいとずっと思っていたんです。1ヶ月飾られている間に、たまに読んでいただいて「あ、この漁師さん面白いな」「すごいな」って思ってもらえたらいいな、と。
― 書籍は、そうすると全く違う視点ですね。
唐澤
書籍は、編集の宮崎くんのコンセプトがすごい面白いと思ったんですよ。
写真家は10名全員に話を聞こうと。そして、僕が制作に関わる前の、第1作目の藤井保さんの時のプロデューサーの方にも話を聞こう、全部最初から聞き直そうと。つばき会さん、漁師さん、さらに写真家さんと、描く対象がぐんと広がったんですよ。だからそこがもうまるっきり違う。しかもカレンダーは写真が主だったから、言葉で描写をするのはこれまでと全く違う感じです。
― 例えばつばき会に関しても、それまでとは異なる発見はあったのでしょうか?
唐澤
知らない話がたくさんありました。震災後、真っ黒な海に真っ白い船が戻ってくるのを見て希望を感じたお話とか。「気仙沼の女たち」を描きたいと思っていた頃は、それぞれをひとりの人物として認識していたのが、改めて話を聞く中で「気仙沼であのことを経ている人達」という風に変わりました。
僕ね、震災後ボランティアに参加したわけでもなくて、「震災のことを自分が描いていいのか」というのがずっとあったんですよ。
元々エンターテインメントの仕事をしていたので、芸人を取材することが多かったんですが、ラベリングをするのがすごい嫌いで。例えば「じゃない方芸人」みたいな言われ方とか、その人たちをコンビで面白いと思ってきたのに、「じゃない方だから」みたいな聞き方をするのがすごく嫌だったんです。
だから意識的に「被災地だからこう」みたいな聞き方を、漁師さんに接する上でもつばき会さんに接する上でもしたくない、というのが前提にあったんです。
だけど、この本はそこからもう逃げられないですよね。漁師カレンダー10年間の始まりが震災がきっかけで、斉藤和枝さん、小野寺紀子さんおふたりの熱い想いから始まってるんで。話を聞いていくうちに、これはもう、まるでその場にいたかのように描けたらいいなと思うようになったんです。ちゃんとこの痛みも描かないと、あの人たちの笑顔が伝わらないと思ったので。だから、本当にティッシュ3箱なくなるぐらい泣きながら書きました。
そこが、これまで僕が中心としてきた「インタビュー」との最大の違いで、個人的にはすごい難しかったですし、面白かったことですね。言葉だけじゃなくて、その描写もしたいと思ったので。
― 読んでいて、本当に紀子さん和枝さんたちの当時の映像が目に浮かぶようでしたが、それは唐澤さんにとっても挑戦だったんですね。
(後編へつづく)
この度実現した「海と生きる」著者、編集者へのインタビュー。
後編では、書いていく中で、著者・唐澤和也さんが、編集者・宮崎幸二さんとどのようなやりとりを重ねたのか、旧知の仲だからこその濃厚なラリーのお話や、写真家さん達の取材で感じたこと、そしてこの本にこめた思いを聞かせてもらいました!

